ロマンス小説を多く翻訳している翻訳家 佐竹史子さん
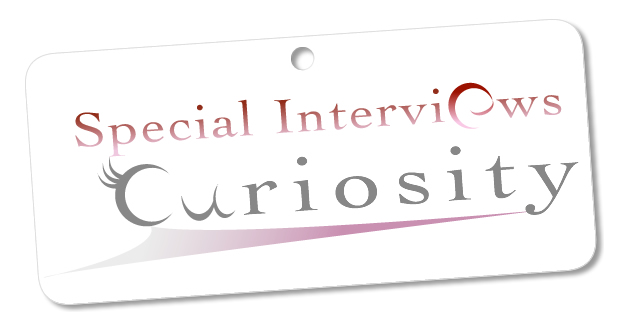
Warning: Undefined variable $checkSmartListPost in /home/onebilling/cuemovie.com/public_html/wp-content/themes/newstube-cuemovie/html/single/content.php on line 77
はじめに〜海外ロマンス小説の秀作「レベッカのお買い物日記」シリーズと出会って
キューティー映画の原作小説はできるだけ読むようにしています。そしてキューティー映画の原作だけではなく「映画原作になりそうな」キューティー映画系小説(ロマンス小説のことですが、ここではあえてこう呼ばしてもらいます)も多く読むようになりました。
しかし英語で読めないので、翻訳され日本で出版されたものに限られます。
そんな時に出会ったのが、ソフィー・キンセラ著「レベッカのお買い物日記」でした。
[429] [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/getitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response: {"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
とにかく文体が軽やか。すぐにでもキューティー映画として映画化出来そうな内容で、人物の造形や話の展開も素晴らしく、いっぺんにお気に入りになりました。後に「レベッカのお買い物日記」は『お買いもの中毒な私!』というキューティー映画になります。
この映画の感想で、ほとんどを原作について書き連ねたくらいです(笑)
ソフィー・キンセラの他の著作も読みました。その中でも「エマの秘密に恋をして…」はほんと面白いです。
こちらもやはり構成が上手い。クライマックスが映画的で、どんでん返しの爽快感が素晴らしいのです。おすすめです。
で、この面白さってなんだろう?と思いました。ソフィー・キンセラ自身の言葉で読んでいません。あくまでも「ソフィー・キンセラが書いた英語の文章を翻訳したもの」を読んで楽しんでいます。
となると、翻訳家さんの個性やセンスが重要になってくるわけです。ソフィー・キンセラの著作や『プラダを着た悪魔』の原作など、多くのキューティー映画の原作やキューティー映画系小説の翻訳で「佐竹史子」という名前があることに気付きました。どうも自分が楽しんでいるのは、この佐竹史子さんの翻訳した文体なんじゃないかな?と思うようになりました。
キューティー映画系の内容となると、流行りやブームも理解している必要があります。コメディ系で重要な、女性同士の会話のキャッキャ感なども違和感なく日本語化する必要もあります。ビジュアルも付随してくる映画の字幕翻訳とは違い、全て文字で表現する小説の翻訳でそれを読ませて楽しませるのって、どんなテクニックがあるんだろう?と。小説翻訳について色々聞いてみたいと思いました。
そこでソフィー・キンセラの著作を出版しているヴィレッジブックスさんを通じて、ソフィー・キンセラの著作の他にもキューティー映画の原作本などを多く翻訳している佐竹史子さんにインタビューすることにしました。
佐竹 史子 プロフィール
1966年生まれ。早稲田大学第一文学部卒。翻訳家。おもな訳書に、ベル『恋はベティ・ペイジのように』(集英社)、ヒギンズ『最悪で最高の恋人』、マクリーン『王国の花嫁』(以上竹書房)、ワイズバーガー『プラダを着た悪魔』(早川書房)、キンセラ『レベッカのお買いもの日記』シリーズ5作、『エマの秘密に恋したら…』『本日も、記憶喪失。』『家事場の女神さま』(以上ヴィレッジブックス)などがある。
翻訳家になるまで、と、なってから
佐竹さんが翻訳をすることになったきっかけを教えて下さい。
大学は心理学科だったんです。4年生の時に大学院に行こうと思ってたんですけど、チョットなんとなく無理かな…とか思って(笑)
それに気付いた時には就職活動の時期が過ぎてたのと、もともと本が好きだったので、翻訳学校に通ってバイトをして何とか…って思って。
元々海外小説はお好きだったんですか?
カーソン・マッカラーズ ((カーソン・マッカラーズ:1917年生まれのアメリカ人女流作家。主にアメリカ南部を舞台にした小説や戯曲、詩などを発表した。同性愛者だったが同じ男性と2度の結婚歴がある。映画化されたものに1967年『禁じられた情事の森』1968年『愛すれど心さびしく』がある。))の「結婚式のメンバー」「悲しき酒場の歌」とか、アメリカの南部を舞台にした、社会の底辺に生きる市井の人達を描いたものが好きでした。
フランソワーズ・サガン ((フランソワーズ・サガン:1935年生まれのフランス人女流小説家・脚本家。18歳の時に書いた『悲しみよこんにちは』が大ヒット。そのせいで若くして成功し薬、酒、病、男、女、あらゆるゴシップに名を連ねた。))も好きで読んでました。
集団の中からあぶれちゃった人たちの話とか好きなんです。
私自身、集団とかに馴染めないタイプだったんですね。だから本を読むと凄く癒やされたんですよ。海外小説だと日本とは違う景色を文章から感じられることが出来たりして、現実感からの飛躍じゃないですけど、想像の羽が広がったんです。
そして「どこかに友達はいる」って本を読んで思いながら(笑)
私…なんて寂しいやつだったんだろっ!(笑)
その時の心で感じたことを自分もできたらいいな、て思ってましたね。
お仕事の最初の頃はどうでしたか?
リーディングっていう仕事がありまして。
本を1冊読んであらすじを書くんです。そして、その本についての感想も書くんです。
単なる感想じゃなくって、客観的に本の魅力を伝えないといけないんです。それを最初の頃かなりやりましたね。
1冊読んであらすじをまとめるって最初「どうしよう!大変だっ!」って思ってましたね(笑)
出版社と直接何十本もリーディングの仕事をやっていると、そのうち出版社の人も「この人はこういうのが得意だな」っていうのがわかってくれるんで、そこから翻訳の仕事が来るようになりました。
翻訳家さんって小説のあとがきで簡単なストーリー説明と解説を書かれるじゃないですか。「その辺のノウハウはどうやって培われてきたんですか?」って聞こうと思ってたんですよ。それがそのリーディングなわけですね。
そうです。だからよく分かんなくて適当なリーディングをして凄く出版社の人に「これはどうしてこうなってるの?」とか突っ込まれたり。
電話で色々1時間位聞く出版社の方もいて、しんどかったですねー。
でも、それより何より海外の本をいち早く読めるっていう喜びの方が大きかったです。
非常に苦しくて楽しかったっ、て感じ。
Warning: Undefined array key "description" in /home/onebilling/cuemovie.com/public_html/wp-content/plugins/wp-hamazon/app/Hametuha/WpHamazon/Constants/AmazonConstants.php on line 319
Warning: Undefined array key "description" in /home/onebilling/cuemovie.com/public_html/wp-content/plugins/wp-hamazon/app/Hametuha/WpHamazon/Constants/AmazonConstants.php on line 319
Warning: Undefined array key "description" in /home/onebilling/cuemovie.com/public_html/wp-content/plugins/wp-hamazon/app/Hametuha/WpHamazon/Constants/AmazonConstants.php on line 319
Warning: Undefined array key "description" in /home/onebilling/cuemovie.com/public_html/wp-content/plugins/wp-hamazon/app/Hametuha/WpHamazon/Constants/AmazonConstants.php on line 319
Warning: Undefined array key "description" in /home/onebilling/cuemovie.com/public_html/wp-content/plugins/wp-hamazon/app/Hametuha/WpHamazon/Constants/AmazonConstants.php on line 319























